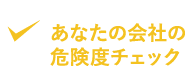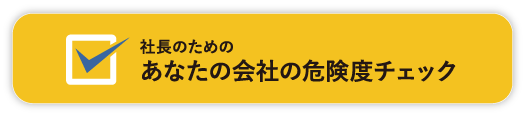∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ5月1日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
■覚悟の瞬間(とき)出演■
http://www.kakugo.tv/person/detksj3zb.html
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年5月20日(土)
2017年6月17日(土)
2017年7月15日(土)
2017年8月19日(土)
【大阪】
2017年7月29日(土)
2017年10月28日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)終了いたしました
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
金融緩和で多くの銀行が
融資合戦をしている。
貸せる会社には
必要以上にドンドン貸付けてる。
新規の銀行が来て
融資提案をしてくる場合も多い。
断るのも1つの方法、
融資を受け入れて既存銀行に
揺さぶりを掛けるのも1つの方法、
その会社の事情に合った方法で
上手く利用した方が得策だ。
銀行は競争させることで
有利な条件を手に入れる事が出来る。
1行取引をしていると
銀行が横暴になる。
大概、1行取引は金利も高い。
戦略的銀行交渉をする事で
保証協会付け融資を減らし
プロパー融資を減らせる
チャンスかもしれない。
担保設定を見直し、
担保を外せるチャンス
に出来るかもしれない。
既存の借入の金利は髙いか、
担保の設定状況はどうか、
保証協会付融資か、
プロパー融資か、
保証人は誰か、
返済期間を長く出来ないか
借入増額が出来ないか、
などよく吟味をして
戦略的な銀行交渉をして
いい条件を勝ち取ることだ。
必要な借入をしない方がいいかと
相談を受けた。
私の回答は、借入ものなら借りておけだ。
返済はいつでも出来る訳で、
借入はいつでも出来ない。
無駄に使わず、
流動性で預金しておけば
銀行の評価は更に高くなる。
他行がこんなに貸しているなら
大丈夫だろうと
更に銀行が寄って貸し出す。
相乗効果を生む。
銀行の心理を付いた
借入方法をとれば
必要以上に借入出来る。
金利は必要経費だと
思えるようでないと
多くの借入は出来ない。
必要でないお金を借りて
金利を払うという事は
銀行に対して貸しをつくると言う事だ。
恩を売れる時に売っておけば
必ずその見返りが返ってくる。
中小企業経営者が
銀行を操れるようになれば
事業拡大も楽になるはずだ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する復元力する力を持つ経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
会社の危機が訪れる時がある。
事業はいつまでも順調とはいかない。
その時の対処次第で
会社が潰れる時もある。
その時に大切なのは、
復元力があるかどうかである。
車で事故をした時に
車のボディーがへこんだ。
そのへこんだボディーを
元の形に戻す力を
復元力と言う。
突発的な難題が降りかかった時に
自分の人生からの経験を通して
どう考えるかがまず第一である。
考えた結果、どう対処するかにより
会社が復元するかである。
危機に対してどう考え、
どう行動し、どうリスクを避け
危機をはねのけることが出来るかが
その経営者の復元力の差である。
急に復元力が身に付くわけではない。
常に失敗を想定した経営を
してない限り復元力は身に付かない。
多くの経営者は成功する事ばかりを考え、
失敗する時の事を想定してない。
自分は成功すものだと言う前提で
事業をされている方が多い。
事業で成功する確率は
恐らく5%以下だろう。
失敗することの方が多いのだから
本来は失敗する事を前提に
その対策を考えておくべきだ。
会社が倒れない程度の失敗を
多く重ねていく事が
復元力を身に付ける手段でもある。
復元力が経営者の底力である。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ プロラタ返済で異議を唱える銀行
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
資金繰りが苦しくなると
リスケを申込み事がある。
全行元金返済無しならいいが、
少額返済をする場合に
メイン銀行からプロラタ返済を
希望されることがある。
貸出金額に応じた比率で
返済する元金を振り分ける
と言うのがプロラタ返済である。
このプロラタ返済と言うのは
平等の様に見えるが
実際は平等ではない。
銀行間で不平不満が出る。
メイン行がかなりの比率で
貸出をしている時は
多くの不満がでる事が多い。
それぞれの銀行のリスク度に
差があるからだ。
担保カバー率や保証協会付け融資率など
銀行によってはリスク度が大きく違っている。
リスク度が髙い銀行とリスク度の低い銀行と
同じように扱うのはとても不平等である。
以上の様な事を鑑みて
交渉の順番や交渉方法を変える必要がある。
メイン行の言われるがままに交渉すると
軋轢がうまれて今後の経営に影響する。
担保カバー率・保証協会融資比率
金利や定期・積み立ての預金など
各行の表を作成して
中立な立場で平等は何か考えてみる。
全行が納得できるリスケの組み立てを
考えて交渉すべきである。
これだけはマニュアルに沿って
交渉してくださいと言うものではない。
それぞれの状況に応じて
最適な交渉を選択すべきだ。
中小企業経営者側から考えると
将来のリスクを考えて
保証協会付融資を優先して返済したい。
しかし、銀行はリスクの多い
プロパー融資を優先的に返済してほしい。
リスケ後の戦略を考えて
交渉しないと痛い目にあう。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 個人のお金を会社に入れるとダメになる
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
中小企業経営者の相談を多く受けていると
ダメになる会社のキッカケがある。
それは会社の資金繰りが苦しくなり
個人的なお金を会社に入れて
帳尻を合わしている会社である。
本来会社というのは
会社のお金で賄うものである。
足らない時に銀行融資を受けて
資金繰りを改善して事業継続をする。
会社のお金が足りないからと言って
個人的なお金を会社の入れて
資金を回しているのは
会社ではなくパパママストア―である。
パパママストアーから脱皮して
会社経営をしない限り
事業として成り立たない。
初めはしょうがないと思いつつも
それが当たり前の経営になっている。
銀行の返済をしなくてはいけない
支払いを遅れてはいけない
そう言う真面目な気持ちから
将来のリスクを考えず資金投入する。
今まで貯めてきたい預貯金や
先祖代々の資産を売却して
帳尻を合わすことをしてしまう。
喜ぶのは銀行だけである。
最終的に全ての資金や資産を失い、
身動き取れなくなる。
もう余裕資金が全くなく
再生するための資金も枯渇している。
それでは早く・上手く再生も出来ない。
私が負債140億から復活できたのは、
1円も会社に入れるなと
家族に号令を掛けて
再生に取り掛かったからである。
万が一、失敗しても再起する方法を
先に考えていた。
個人的なお金や資産を
会社のために投入し出すと
赤信号が点滅すると考えて欲しい。
その前に手を打つことをして欲しい。
個人資金を会社に投入する行為は
自爆テロでとても危険な行為だと
認識してほしい。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年7月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年10月28日(土)13:00~15:00(受付12:00~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場 終了いたしました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【営業力だけでは行き詰る】
優れた営業力を活かし
独立した経営者が多い。
勢いが有る時は
それで何とかうまく行く。
何か問題が生じた時、
売上が落ちた時や
トラブルに巻き込まれた時など
どうしていけばいいかわからなくなる。
銀行に対しても
どう対応したらいいか
分からなくなる。
相談にお見えになった経営者も
営業でNO1となり独立した。
売上をつくる事には長けている。
会社を管理する能力や
経営する能力を研かず
売上を伸ばすことを第一として
数年頑張ってきた。
会社の中身も見ないで
とにかく頑張って来られた。
周りからこのままでは潰れる。
破産した方がいいと言われ
どうしたらいいか悩んで
様々な本を読んだ。
私の本を読まれて
最終的な判断を仰ごうと思い
相談にお見えになった。
周りは拡大し過ぎて
借金が増えすぎている。
急拡大したから心配している。
尚且つ、昔の負の遺産もある。
これからどうするのかと
外野席がうるさいらしい。
借入をしたことがない、
商売を成功させたことがない、
そのような人の意見を聞くより
自分に信念があるかどうかだと。
業界で競合他社が殆ど居ない
NO1の絶対的地位を築けるなら
何も怖くないと申し上げた。
その点で自信あるなら、
後は経営者として環境整備と
経営力を高めて
戦略的に銀行交渉をする力を
身に付けることだ。
商売には勝負時と言うものがある。
この勝機を逸した時には
もう後退するしかない。
だから、今がチャンスだから
攻めていくしかないと励ました。
最後には元気が出てきたと帰られた。
自信を持っていただき
前に進めるのも私の仕事と考えている
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ4月24日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
■覚悟の瞬間(とき)出演■
http://www.kakugo.tv/person/detksj3zb.html
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年5月20日(土)
2017年6月17日(土)
2017年7月15日(土)
2017年8月19日(土)
【大阪】
2017年7月29日(土)
2017年10月28日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)終了いたしました
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
会社は20%の頑張っている社員が
残りの80%の社員を養っていると言われる。
蟻の世界でも20%の働き者の蟻と
サボっている80%の蟻が存在する。
その20%の働き者の蟻だけを集めると
やはり80%の蟻は働かないと言う。
人間の世界でも一緒だそうです。
つまりすべてに当てはまる理論である。
売上の構成比を見ても
上位の20%の商品が、
売上の80%を占める。
自社商品やサービスは、
何が80%占めるかを検証すればいい。
営業でもそうですが、
何に注力すればいいか
全く考えず行き当たりバッタリの
営業をしている会社も多い。
仕事に無駄があると
成果や効果も薄れるだけである。
今、何をすべきかを絞り込むことだ。
数字で目標をキチンと定めて
その目標に向かって達成させる。
プログラムを組織化することで
毎日チェックして達成をさせる。
仕事に無駄は禁物である。
大砲を放っても
空砲では意味がない。
目標を定めて命中度を
高める必要がある。
それが勝利の方程式だ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 中小企業支援協議会で解決しない
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
誰でも責任追求から逃れたい。
銀行員も同様で責任回避したい。
だから中小企業支援協議会を活用する。
心底から中小企業を救うために
活用している訳ではない。
先日も支援協議会に行っているが
何も解決策が見えない
どうすればいいかと相談に来られた。
今まで同じような相談で
多くの中小企業経営者がお見えになった。
中小企業支援協議会へは
銀行に紹介されて行く事が多い。
銀行から紹介された認定業者である
税理士や中小企業診断士やコンサル会社で
経営改善計画を策定してもらう。
何の為かというと
リスケをスムーズにいかす為です。
中小企業支援協議会の当初の目的は、
中小企業の真の再生復活でした。
銀行と取引先が協議を重ね
将来の再建策を考え、
その結果リスケをするのが本筋だ。
それを外部委託して
経営改善計画を策定してリスケをする。
認定業者がその企業の事を
短期間でわかるとは思えない。
実際は経営改善計画でなく
借入返済計画になっている。
中小企業支援協議会に相談する会社は
債務過多が殆どである。
債務過多を解消したら復活できる
企業が多くある。
分かっていてもしない。
中小企業支援協議会のメンバーが
地元金融機関のOBが多く
天下り先になっているからだ。
リスケでお茶を濁し、
根本的な解決は先送りする。
これが実態である。
根本的な解決を図れないから
いつまで経っても希望が持てない。
中小企業支援協議会に行っても
苦しさから解放されないのは
以上の様な事情があるからだ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ リスク分散しなかった経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
本業が時代の流れとともに
衰退し利益が出なくなった。
海外事業にも手を出したが、
更に借入を抱え、
赤字に転落した経営者が
相談にお見えになった。
活路を見出す為に
新規事業を2つ始めた。
1つは飲食事業のFCをした。
大きく儲からないが、
確実に利益を生むようになった。
もう1つは海外からの食品輸入で
大手商社に売ることが出来て
堅い商売が出来るようになった。
本業の借入が重たくて
毎月の返済が多すぎて
どうにもならない。
リスケをすると海外事業の
折り返し資金が出なくなる。
痛し痒しの状態である。
苦しみから抜け出せない。
今までリスクヘッジを考えず
新規事業を既存会社で行った事が
今となっては身動き取れなくなった。
完全別会社で新規事業をしていたら、
本業を捨てて新たな出発が出来た。
大きな借金と言う荷物を背負いながら
全速で走らなくては倒れてしまう。
本業がダメになるのを見越して
新規事業を立ち上げて
模索していくのは間違いではない。
しかし、同じ会社ですると
重荷を背負う事になる。
将来のリスクを考え、
どういう形態で新規事業をするか
大きな分かれ目になる。
ここを間違うと四面楚歌状態に陥る。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 戦略的銀行交渉が出来ずに法的処理に
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
銀行が何を考えているのか?
銀行が次に何をするのか?
これがわからず
事業が上手く行き出したのに
法的処理をされてしまった
経営者が相談にお越しになった。
中小企業経営者の多くは、
金融について詳しくない。
何とかなると思って
対応が遅れる事がある。
それが命取りになる。
相談にお見えになった経営者も
最後の最後で交渉すればなんとかなると
放置していたところがある。
その結果競売手続きをとられた。
法的な手続きに入ってからは
銀行として急に止められない。
この先どうなるかわからず
対処法の知識も無く
不安に駆られる。
仕事が上手く行き出したとしても
全てを失う恐れが出てきた。
法的処理前なら
いくらでも対処法があり
これ程悩む必要も無かった。
戦略的な銀行交渉をせず
いい加減な対応をしていると
最後に痛い目にあう。
銀行はギリギリのところまで
待ってくれる姿勢を示す。
それでもダメと判断すると
損をしても処理の道を進む。
銀行を舐めてはいけない。
銀行が考えている先を予測して
先に行動する事が大切になる。
それが出来るかどうかで
会社の存続を左右する。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年7月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年10月28日(土)13:00~15:00(受付12:00~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場 終了いたしました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【成功する頼まれた事を迅速にこなす経営者】
人に依頼されたことを
どう対処するかで
その人の評価も変わる。
20代の頃、信用も人脈も無い時に、
人生の大先輩から色々頼まれた。
その頃と言うのは、
お金も力も無く、
無い無い尽くしでした。
依頼されたことに応えるしかなかった。
その先輩が教えてくれた。
人に依頼されたことをどう応えるかで
あなたの評価が変わる。
だから、実直に対応しなさいと教えられた。
私の後輩でとても優秀な経営者がいる。
彼にものを依頼すると
必ず、キチンとした返答をしてくる。
しかも、迅速に行われる。
その後輩はドンドンと
商売も拡大していっている。
中小企業経営者の相談を受け
サポートをさせて頂いてますが、
依頼したことを迅速に対応する経営者は、
必ず成功の道を駆け上がる。
やらなければならない事を
なかなかやらない経営者は
浮上する速度が遅い。
忙しいとか色々と言い訳を言われる。
言い訳をして済めばいいが、
倒産しては意味がない。
時間との闘いでスピード感が
とても重要な復活の条件となる。
勝負事もそうですが勝機を逃したら
逆転して勝つ事が難しい。
何事も迅速に対応するのは
成功する経営者の必修条件である。
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ4月17日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
■覚悟の瞬間(とき)出演■
http://www.kakugo.tv/person/detksj3zb.html
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年5月20日(土)
2017年6月17日(土)
2017年7月15日(土)
2017年8月19日(土)
【大阪】
2017年4月22日(土)
2017年7月29日(土)
2017年10月28日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)終了いたしました
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
利他の精神がある経営者は
非常に魅力的である。
自我の欲ばかり求めている
経営者は尊敬の対象にならない。
滅私奉公という言葉があるが、
若い時代は滅私奉公することが
とても大切ではないかと
経験上思っている。
20代の頃は
お金も名誉も実力も何も無かった。
自分が出来ることを惜しみなく
相手に奉仕するしか恩返しは無い。
自分より年配の方に
凄く可愛がってもらった。
何か頼まれたことはとにかく誠意を持って対応した。
そして、よく会食に誘われた。
「NO」と言う返事はしなかった。
何時でもお付き合いした。
素晴らしい方を
次々に紹介してくれた。
いつしか自分の素晴らしい
人脈が形成されていった。
後々大きく花が咲いた。
利他の精神とは、
相手の利益や便宜を重んじて
自己を捧げる心構え。
何の見返りも求めない。
その素晴らしい利他の精神をお持ちの
先輩経営者のお蔭で成長させて頂いた。
その経営者は時には厳しい事を言われるが
いつも温かい目で見守ってくれている。
そういう経営者の周りには
何かお返し出来ることは無いかと
いつも取り巻きが一杯いる。
私にとって人生の師であるので、
見習いながら勉強させてもらっている。
そういう厳しく優しい尊敬できる
怖い存在がいることに感謝している。
最近は厳しい事を言う人を避けて
気が知れた仲間だけ付き合い人も多い。
特に経営者は様々な人と付き合う。
自分と価値観が違う、厳しい事も言う
居心地の悪い人の中にも飛び込んだ方がいい。
必ず将来活きる時が来る。
利ばかり求めいると
人もお金も情報も寄ってこない。
利の前に自分が出来ることを奉仕する。
そうすれば後々何倍もなって返ってくる。
目先の事だけを追っていると壁にぶち当たる。
経営者には利他の精神が大切だ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する考えて人を動かす経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
経営者の中には、
何から何まで知っておきたい
ワンマン(カリスマ)的な経営者と
人を育て活用することに長けた経営者と
大きく分けて2通りいらっしゃる。
ワンマン的な経営者は、
現場に精通している思いが強く
細かくイチイチ指示を出して
全てに渡り仕切ってしまう。
つまり従業員は自分で考えず、
与えられたことだけをこなす。
余分な事は一切しない。
その反対で
人を活用する経営者は、
数字や結果に基づいて
目標や成果が得られなかったら、
なぜそうなったかを質問する。
どうすれば目標や成果を得られるかを
自分たちで考えて回答を求める。
つまり、自分の頭で考えて行動させる。
従業員に責任ある行動を求める。
ワンマン的な経営者が
社員に頑張れと言っても何も出来ない。
受け身の仕事しかしてきてないからだ。
当然、結果も出ず低迷を続ける。
考えることを訓練して来なかったから
何をしたらいいかわからない。
人を活用して動かすタイプは、
目標達成のために
多くのアイデアを出させる。
全てさせて失敗を繰り返しても
検証をする事で成功法則が見える。
最後には大きな成功を手に入れる。
高学歴の素晴らしい人材が
役所や大手企業に行って、
脳死状態になっているのを良く見かける。
大企業病に罹ってしまっている。
人は考えるから成長する。
考えて実行して検証して
そして、修正して実行して
精度を高めていく。
失敗こそ成功の元で
大きな財産だと認識すべきだ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 銀行ばかり返済して行き詰る経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
飲食店を30店ほどチェーン化されている
経営者が相談にお見えになった。
東京で知名度のあるチェーン店です。
20年ほど前に1店舗目をオープンし、
順調に売り上げも利益も伸びて
銀行の後押しで出店攻勢をかけ
30店舗以上に拡大していった。
ところが競合店が多くなり、
店のコンセプトとお客様の望むものが
少しずつズレていき、
売上も減少し出した。
赤字店舗も増えて
赤字店舗の撤退もしていった。
元々の借入方法が間違っていた。
飲食店の出店借入を
3~5年返済の資金で借入していた。
昔と違いそれ程短期に回収できるほど
飲食店は利益率もよくないし甘くもない。
都銀がメイン行になっており、
厳しい返済計画になっていた。
融資をしてくれるなら凌げると思い、
店の根本的な改革をせず、
お客様から段々と飽きられていった。
流行の店ではないですが
飲食店と言うのは
必ず飽きられていくものです。
飲食店も革新を遂げないと行き詰る。
ただ値引きだけの販促に頼り過ぎて
利益率が下がり
利益を圧迫する結果となった。
昔ながらの商法に頼っている。
資金繰りが苦しくなり、
銀行借入を何とか継続させるために
銀行返済を優先し、
取引先や税金・社会保険などを
滞納してしまった結果、
融資も断られてピンチとなった。
銀行に責められ、
取引先に責められ、
税務署に責めれら、
社会保険庁に責められ、
四面楚歌状態です。
リスケをしても
税金や社会保険料の滞納、
取引先への支払い延滞など
経営を圧迫していき、
八方ふさがりの状態だ。
利益を出している今の間に
お金の回し方を変えていき、
次のステージへ持っていかねば先はない。
この様な状態に陥った相談は絶えない。
銀行が融資してくれなかった時の恐怖を感じ
銀行だけはきちんと支払って行かないとダメだと
錯覚している経営者が多い。
取引先があるから商売が出来る。
税金や社会保険料の滞納は
高額な延滞金が課せられると共に
延滞していると融資も受けられない。
何事にも優先順位と言うのがある。
その優先順位を間違うから
この様な八方ふさがりの状態になる。
更に中小企業の場合に
どの銀行と付き合い
どの銀行をメインにするかで
経営の手法も変わる。
困った時に救ってくれる銀行を
選ぶ、そして、救ってくれるような
付き合い方をしておくことが
とても大切になる。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 会社からの借入金で融資ストップに
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
地方出身で東京進出して何十年となる
建設関係の経営者が相談に来られた。
東京では支店登記もせず、
地元の地方信用金庫で
数千万を借入をしてきた。
創業者である父親に対する貸し付けが
4000万以上存在していた。
給与を余り取らないで
会社からの借入ばかりして
お金を回していた。
膨大に膨れた貸付金が
銀行として放置できなくなった。
経営者が会社からお金を借りているのは、
全て不良債権を見なしてしまう。
会社に返済されないだろうと見る。
決算書でマイナスに該当する項目を
銀行は差し引いて決算書を見る。
この会社は貸付金をマイナス処理すると
債務超過に転落する。
債務超過の会社に該当し貸付けできない。
経営者が会社を食い物にしていると見られる。
利益を出して貸付金を返済していきなさいと
恍けたことを言っていると
この会社は資金ショートする。
どういう手法をとるかによって
この会社の将来が決まる。
地方の地元銀行で長く付き合ったが
二代目になった訳だから
地元を支店にして
東京に本店登記することを申し出ると
一括で全額返済しろと脅された。
支店ではお金は貸せないと言い出した。
メイン行で優位な立場を
崩されたくない一心で
責め立ててきた。
今までどんぶり勘定をしても
儲かりお金が回っていた
先代の時代と違う。
いい時代で守られた業界の会社は
この様な会社が多い。
後継者がかなり苦しんでいる。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年7月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年4月22日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年10月28日(土)13:00~15:00(受付12:00~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場 終了いたしました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【成功するクレームに耳を傾ける経営者】
昔と違って気に入らない事を
主張した方が勝ちの様な風潮がある。
商売上クレーマーの対応が
昔と違って非常に難しい。
クレームの中にも隠された宝がある。
その宝を探し当て
次に活かせば
素晴らしい結果が残せる。
節度の無いクレームが増え、
クレーマー対応で時間がかかり
精神的苦痛から担当者も
本来の仕事が出来なくなっている。
ある学校の教頭と話をした時に
学校で生徒を注意するのも大変らしい。
生徒の中には生まれてから
誰にも叱らえた経験が無い子供が
クラスに3人は居ると言っていた。
注意することもままならない。
本来の教育が出来ない上に、
責任だけが多く被されて
とてもやりにくいと訴えていた。
志ある教育者が現場から去り、
教育現場も空気が変わって来たと
嘆いておられた。
経営においてもお客様の声を
どのように吸い上げるかが
とても重要になってくる。
本当のクレームや意見を
どのようにして嗅ぎ分けるか
工夫してキャッチするしかない。
その意見をどう商売に反映し、
求めているお客様に
伝えることが出来るかが
勝負になってくる。
クレームや意見を蔑には出来ない。
そこに大きな宝が眠っているからだ。
飲食店を経営していた20代の頃
お客様のクレーム(意見・要望)を報告した店員に
報奨金を渡して活用していた。
そこには営業上のヒントがあり、
活用した結果売上が3割増えた。
何もクレームも言わずに
二度と来なくなるお客様がたくさんいる。
そこを改善しないとお客様は
ドンドン黙って去っていく。
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ4月10日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
■覚悟の瞬間(とき)出演■
http://www.kakugo.tv/person/detksj3zb.html
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年5月20日(土)
2017年6月17日(土)
2017年7月15日(土)
2017年8月19日(土)
【大阪】
2017年4月22日(土)
2017年7月29日(土)
2017年10月28日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
値段の高いものを売るのは、
至難の業である。
高度成長時代で
ものが無い時代なら
まだまだ飛ぶように売れた。
車も1000万台売れていた時代から
500万台に半減している。
着物の販売額も
最盛期に比べて6分の一である。
あらゆる高額商品が売れなくなっている。
売れない車も
シェアや残クレジットなど
使用者の要望に沿って
売り方が変わってきた。
売れなくて困っている経営者も多い。
ある高額のレジャー製品製造販売会社は、
毎年何種類の新製品を出し続けても
売れなくて苦労されている。
売ることに精根尽きてしまっている。
予定通り売れないので
資金繰りが苦しくなる。
打開する為に借入して新製品をつくる。
その繰り返しで借金は減らない。
将来が見えない経営をしている。
今を切り抜くために
一時しのぎ策を講じているだけだ。
売る事をやめる宣言をした。
売る事より借りることを第一に考えた。
借りり方のも色々ある。
他社がマネが出来ない
ビジネスモデルの構築をする。
これしか生きる道はないと
決意し構想を練っている。
『これで先の目標が見えた』
と社長は自信持って動き出した。
発想の転換を図らないと
会社の壁をぶち破れない。
中小企業は経営者次第だ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 借入出来る経営者とは
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
決算書をただ銀行に提出している
経営者は上手く借入が出来ない。
会社の将来像を示さないと
銀行に対しても説得力がない。
相談者の中には、
もがき苦しんだ結果
借入がスムーズにいくように
なった企業も多い。
塾経営をしていた経営者は
少子高齢化で売上も減り
将来に対して不安を抱えていた。
地元への信用力と
学校・教育委員会からの信頼
と言う大きな財産を活かし
児童福祉事業へ転換し
出店攻勢をかけている。
資金的に心配していた経営者も
確実に利益が計上でき
他社の追随を許さないで、
地域NO1へ登りつめた。
上場出来るビジネスモデルも構築でき
当初と全く違う経営者に生まれ変わった。
そこには確固たる将来像があったからだ。
銀行から見て
この会社は成長するなと
思わさないと融資は楽ではない。
事業の成長戦略がないとどうにもならない。
第4次産業革命も起ころうとしている。
AI・ロボット・IOT・ビックデータなどにより
本格的に第4次産業革命が始まると
中小企業でも多くの設備資金が必要になる。
その時に乗り遅れないためにも
早々に収益構造を見直し、
10年20年30年先を見据えた
事業に転換していく必要がある。
銀行を納得させるだけの
確固たる事業の成長戦略が必要となる。
経営者ならそこを考えていくべきだ。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する社員にしつこい経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
成功している経営者は、
大概しつこい。
自分が考えている事を
会社に浸透させるために
何度も何度も同じことを
繰り返し繰り返し伝える。
耳にタコが出来るぐらい
しつこく同じことを言う。
そのしつこさがあるから
会社に浸透していく。
何が大事かを伝える努力を惜しまない。
常に社員やお客様と
コミニケーションをとり
大切な事を伝える。
反面、お客様や社員から
情報を吸収している。
私の知っている尊敬する経営者は
おもてなしの心、ホスピタリー精神を
大事にされている。
そこには一切妥協が無い。
その経営者にお仕えして、
お客様をもてなす立食パーティーを主催した。
料理内容まで厳しくチェックをされる。
その料理でお客様が納得するか、
喜んでもらえるかをいつも考えている。
その会社に行くと
会社全体がおもてなし精神に溢れている。
経営者のしつこさがあったから
社員ひとり一人に浸透している。
1回言ったからいいのではなく。
納得できるレベルまで
言い続ける事をしないと
経営者の想いは伝わらない。
一貫性のあるしつこさと
ブレないしつこさが
成功には大切な要因となる。
経営者のしつこさが
経営全般に浸透して
目的達成のため
大きな原動力になる。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する365日24時間仕事の事を考える経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
働き方や労働時間など
規律を求められている。
雇われ側と同じ様に
経営者自身が
退社したからと言って
仕事の事を忘れれているようでは
会社の将来は無い。
仕事のヒントはどこに落ちているか
分からないものです。
常に仕事の事を考え、
悩んでいると
何処かで未来が開ける時がある。
ふっとした時に思いもよらない
ヒントが舞い降りて来る時がある。
色々な経営者が
私の所に相談にお見えになる。
もがき苦しみが足りないと
思える経営者もいる。
経営者には休みは無い。
経営者には油断は許されない。
特に中小企業経営者にとって
油断は大敵である。
休日だからと言って休んではない。
どこからどこまで休みと言う
明確な線引きはない。
何処か頭の隅で
いつも会社の事を考えている。
脳に汗をかくぐらい考えろと
経営者に言っている。
365日24時間仕事の事を
思い浮かべてないと
いつどこにヒントが
落ちているかわからない。
ノーベル賞に輝いた先生も
四六時中考え没頭してると
思わぬところで光が差して
難題が解決出来たと言う話をよく聞く。
中小企業経営者も同じで、
誰よりも多く悩み考えた人だけが
サクセスロードを歩める。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年7月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年4月22日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年10月28日(土)13:00~15:00(受付12:00~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【成功する朝令暮改の経営者】
経営者は、よく考え方が変わる。
それは常に考えているからだ。。
昔、私自身は全く理解出来なかった。
20代の頃超ワンマンの親父が
コロコロ意見が変わるので、
いい加減にしてくれと思っていた。
経営者なら一度決めたことを
すぐに変えるなと憤りを感じいていた。
年と共に親父のいう事が
理解出来る様になった。
自分自身が経営者になると
父親と同じように
日替わり定食の様に
考え方も変わっていた。
その人の立場にならないと
本当にその人の言っている事が
理解出来ないと先輩によく言われた。
その通りだと思う。
役所が一度決めたことを
絶対に一度決めたことだからと
頑なに進めているのを見ると
朝令暮改の方が絶対に正しい。
役所の様に一度決めたことだからと
押し通しているから
大きな過ちを犯す結果になる。
修正能力がない。
一度決めたことでも
様々な情報が入り、
熟慮した結果、考え方が変わる。
常に考え続けているから
当然の結果である。
何も考えてないから
変更もしないし、
変化もしたくない。
相談者の中には、
考え方を変えられず
会社の調子が悪くなる方もいる。
歴史があり、古い業界程
慣習に乗って商売をしているから
変えられなくなっている。
昨日お会いした顧問先の経営者は
日本伝統の会社を経営されている。
時代の荒波に飲み込まれそうになって
目が覚めた様に考え方が変わった。
今では業界の革命児として
有名になっている。
古き良きものを重んじて
新しいエッセンスを取り入れた
時代に合った商売のやり方を
常に求め革新を遂げている。
とても素晴らしい経営者である。
常に即行動し、危機感を持っている。
だからこそ、5年後の上場を
目指して頑張っておられる。
この仕事をさせて頂き
多くの経営者と出会い、
私自身も勉強させて頂き
とても感謝しております。
今後もお役に立てる様に
全身全霊で知恵を絞り
頑張っていきたい。
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ4月3日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年5月20日(土)
2017年6月17日(土)
2017年7月15日(土)
2017年8月19日(土)
【大阪】
2017年4月22日(土)
2017年7月29日(土)
2017年10月28日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
【悔やまれてしょうがない経営者】
私の本を読んだ経営者が
相談にお見えになった。
食品を扱う年商80億の会社を
経営されていた。
銀行に進められ、
約15億の本社工場を新築した。
その過剰投資が
リーマンショック後に
大きな痛手となった。
リーマンによって赤字になり
資金が回らなくなった。
藁をも掴む思いで
有名な中小企業再生会社に
依頼したそうです。
話を聞いていると
入念な準備もせず
銀行と対峙して
やり合う手法を取った。
どんな戦でもそうですが
準備をしないで戦って
勝てるわけがない。
その再生会社は
銀行の評判が芳しくなく
銀行から政治屋みたいな人で
気を付けた方がいいと忠告された。
経営者としては判断できず、
推し進めてしまい
最終的に大金を取られて終わった。
それだけの規模と100年以上の歴史と
信用力のある会社だから
銀行に理解を求めつつ
再生の道を探れば良かった。
メイン銀行も支援体制で動いていた訳だから
上手く交渉しながら進めるべきだった。
何を守り、どういう手法で行う
基本的なスキームも無く
いきなり銀行とやり合うやり方は
自爆テロの様なものだ。
日増しに追い込まれ、
個人の資金も会社につぎ込み
会社も個人も資産売却させられ
どうすることも出来なかった。
結局、何も残すことが出来なかった
コンサルの社長と喧嘩別れになったそうです。
結局は会社の資産も
個人の資産も全て失い、
サービサーに転売された
大きな債務だけが残った。
サービサー処理方法も
伝授されなかったようで
今後の処理方法を聞きに来られた。
当初は早く本を出してくれていたらと
悔やんでおられましたが、
お別れする時には明るく
元気を取り戻しお帰りになった。
こういう機会に出会う度に
再チャレンジ社会の構築を
一日でも早く実現したいと
心が奮い立つ。
才能豊かな経営者が
一度の失敗で
人生を棒に振るのは
とてもおかしい。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 何も知らずに保証人になった悲劇
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
地方出身で現在は
大病院の外科の責任者をしている。
仕事に対して非常に真面目な
家族思いの医師が
不幸に巻き込まれている。
その方の父は地方で
小規模の総合病院を経営している。
15年程前までは業績も良かったが、
段々と経営不振となり、
追加融資を繰り返し、
債務も大きくなった。
銀行は父の生命保険で回収しようと
プロパー融資を繰り返した。
ところが思惑が外れ父が長生きした。
そのために回収が危うくなってきた。
毎日銀行に攻められてた父は、
精神的に追い込まれて痴呆が進みだした。
銀行は息子が継いで
長く回収をしようと画策をしている。
他の2人の保証人も脅し、
保証人同士が混乱をし、
息子が後継者になるように進めた。
父親含め、保証人を4人もとっている。
今の金融制度では考えられない。
第三者の保証人は求めないと
金融庁が指導をしておりますが、
既に保証人になっているものを
外すことは出来ない。
以上にそこを強調する銀行である。
第三者保証人問題で
困っている経営者は
全国に多くいらっしゃる。
事業をやめるにやめられない。
4人の保証人の中で
相談者が一番回収しやすいから
責めに責めまくってくる。
彼の将来を考え何とかする為に
1つの方策をとることを考えている。
地元の親の病院を引く継いても
赤字から脱却は出来ないし、
過大な借金は到底返済出来ない。
金融機関とすれば
ギリギリまで回収する事を常に考える。
彼の人生は棒に振ることになる。
それは有能な意思を埋没させることになる。
自分が事業をして借金をしたものは
自分でまいた種だからしょうがない。
しかし、そうじゃないものについて
継承させて責任を負わせる保証制度は
法的に禁止することをしないと
債務者は弱いから受けてしまう。
全国の事例を見ても
債権者である銀行から言われれば、
第三者保証人を差し出している。
しかも、自ら保証人になりましたと言う書面に
署名捺印をさせられている。
全く貸し手と借り手は平等ではない。
金融庁も変わりつつ有る様に
時代に添った保証人制度に
抜本的に変えて頂きたい。
何としても制度改革の声を
広げて実現していきたい。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する任せっぱなしにしない経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
部下に任せる事と
任せっぱなしにする事とは全く違う。
その区別を分かってない経営者もいる。
会社には必ずどこかに
緊張感が無いとダメだ。
任せっぱなしにしていると
必ず上手くいかなくなる。
権限移譲して放置してはマズイ。
気が緩み間違いの元になる。
成功する経営者は
しつこくチェックをしている。
必ずフィードバックをさせる。
そこが成功する経営者と
成功しない経営者との違い。
経営者が忙しいから
権限移譲しているだけの所もある。
それは、経営者が楽をするために
権限移譲しているだけで、
人材を育てるとは違う。
中小企業は、経営者以上の人材は
入社して来ないと思っておくべきだ。
だから、育てる努力を惜しまない。
全ての従業員が経営者の思う様に
働いてくれたら儲かってしょうがない。
いかにレベルを上げるかを
常に考えておく必要がある。
定点観測が必ず必要となる。
経営は怠るとどこかで歪みが生じる。
気を抜けないのが経営者である。
365日24時間会社の事を
考えているぐらいでないと
上手く行かないものである。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ いつ動くかで決まる
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
いつ決断して行動するかで
会社の再生は大きく違ってくる。
真面目な社長ほど
個人的な資金を出して
銀行への支払いを続け
会社の存続を願う。
それで会社が復活すれば申し分ない。
個人的な資金が枯渇するまで
大方の経営者は出し続ける。
資金がなくなった時点でジ・エンドである。
つまり、倒産して破産に追い込まれる。
汗水垂らして貯めてきた家族のお金を
銀行の返済のために
使っただけの結果になる。
生きたお金ではなく、死に銭である。
相談に来られた経営者は
まだ枯渇前だったので
滑り込みセーフだった。
多くの個人的な資金を会社に投入していた。
個人的なお金を会社に
入れている経営者は、
復活出来ない場合が多い。
会社に個人的な資金を入れる手法は、
会社経営ではなく、
パパママストア―に域だ。
会社として運営したいのなら
そこから脱した経営をすべきだ。
個人的なお金を入れて
倒産する経営者は、
後々悔やまれる。
次の復活するための資金として
活用した方が有効的だ。
死に銭にするより
人生の再スタートの資金として
生きたお金の使い方をした方が
生命力ある人生に変わる。
是非、人生の先を見て
お金の使い方を考えて欲しい。
そうすれば自ずと道が開ける。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年7月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年4月22日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年10月28日(土)13:00~15:00(受付12:00~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【成功する会社の存在意義を明確化している経営者】
会社の存在する意義が
明確になっているか
とても大切な事だ。
なんのためにその会社は有るのか。
それがはっきりしてないと
会社も社員も誇りに思えない。
成功している経営者を見ていると
自分の会社の存在意義を明確化して
社員にも共有している。
儲けるために会社を経営している。
それではいつか会社もダメになる。
儲けたい儲けたいという一心で
商売をされている方ほど
儲けてない様に見える。
人に喜ばれる
社会に喜ばれている
だから売上も上がり利益も増える。
儲けは後で付いてくるものだ。
厳しい親父が良く言っていた。
20代の時、厳しい親父から
儲けようと思うから儲からない。
損して得すると言う言葉を知らんのかと
よく叱らえたものです。
喜んでもらったら、
後から儲けは付いてくる。
若い時はよく理解出来なかったが、
今はその言葉の意味がよくわかる。
何をもってお客様に喜んでもらうか
これが大事になる。
それが会社の存在意義になる。
それが明確でないと
お客様にもメッセージも伝わらない。
相談者の中に迷い子になっている
経営者がよくいる。
会社をイメージした時に
誰でも共通の認識を
持っているなら問題ない。
会社がお客様に一番訴えたいことは何か?
これが明確でないと将来はない。
立ち止まって
会社の存在意義を見つめなおすことも
とても必要になってくる。
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
負債140億の会社を自力再生した経営者だから言える!
『知らないと損をするメルマガ情報』
モットー【何があっても大丈夫!】 メルマガ3月27日号
株式会社Jライフサポート
”会社と家族を守る”経営 アドバイザー 三條 慶八
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
###name### さん
Jライフサポートの三條です。
いつもメルマガを読んで頂き、
ありがとうございます
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
◆新刊2冊発売中◆
╋・誰も教えてくれない・╋
あなたの会社の お金の残し方・回し方(フォレスト出版)
借金回収リーマン日記(徳間書店)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
●出版記念セミナー● 詳しくはホームページをご覧ください
【東京】
2017年4月5日(水)
2017年5月20日(土)
【大阪】
2017年4月22日(土)
【福岡】
2017年4月15日(土)
【北海道】
2017年5月13日(土)
【仙台】
2017年6月10日(土)
【名古屋】
2017年7月8日(土)
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
なかなか先が見えない経営者が
相談にお見えになった。
老舗の会社であるが、
何年も赤字続きで大きな債務超過を抱え、
銀行からも責められ、
資産売却をして凌いで来た。
最盛期に比べて売上が5分の一に減っている。
設備は最盛期のまま維持して生産している。
商品の種類も最盛期以上にある。
工場稼働率は50%以下である。
工場から商品が出荷した時点で
赤字になっている。
作れば作るほど赤字になる状態である。
そのために売上を上げて原価率を下げ
利益を確保する必要がある。
当たり前の話である。
今までのコンサルもチャレンジした。
社長に工場に入って現場を知れとか、
店頭に立ってお客様の声を聞けとか
色々な事を苦言されたそうです。
しかし、赤字の垂れ流し状態は続く。
正常に黒字化し、
借入を返済出来る状態にするには
売上を3倍にしないと困難である。
余剰資産も無い、
資金も無い、
税金や社会保険も滞納している。
銀行・税務署・社会保険庁の3方面から
責め立てられている。
会社の大構造改革をしようにも
資金がない。
今の続ければ続けるほど
赤字が増えて資金も流出し
材料も仕入困難に陥る。
お金も無く、悠長な事を言ってられない。
今までのコンサルが言っていたように
少しでも売上を上がるような
施策を考えていく手法では
時間的に間に合わない。
社長に質問しました。
5年先10年先
会社をどうしようと思っていますか?
回答は、
そこまで考える余裕が無い。
今目の前の事で精一杯です。
今のままの状態を続けて、
5年先10年先会社があると思いますか?
5年先には会社はない。
今年の末には無くなっている可能性もあると
現状を認識してもらった。
言いたかったことは、
小手先の事をして将来はない。
根本的な解決を図らない限り
社長(経営者)の未来はない。
社長(経営者)の残りの人生を考えて欲しい。
倒産して、破産したら、
地域では知名度ある名士だから、
精神的にかなりきつい。
社長を雇う会社はないはずです。
何故なら、重たすぎる人材だからです。
家族を守る為にどうして稼ぎますか?
今のままなら、静かに死を待つしかない。
以上の様な話を懇々と話をしました。
超エリート育ちでしたから
私から言われるのも嫌でしたでしょう。
社長の決意と覚悟がないと何も出来ない。
現実を知ってもらわないと思い、
厳しい話をしました。
小手先の指導だけして
結局、社長の努力が足りなかったですねと
逃げることは簡単だが
それでは本当のサポートにならない。
中小企業経営者の再生は、
人生の再生だからです。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する失敗を責めない経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
世の中、失敗しると
叱る・怒る・愚痴る人は多い。
それは逆効果である。
やる気が失せてしまえば
元も子もない。
怒りまくっていた上司は、
昔はよく見かけた。
父親は典型的な昔気質の経営者で
パワハラ全開でした。
怒る時は社長室に呼ばれ、
2時間大声で怒鳴られ罵倒された。
最後には「会社をつぶす気か」と責め立てられた。
夜中であろうと
自分が気になることがあると電話をしてくる。
『あれはどうなっているだ』と
怒りだす始末です。
昼ごはんも悠長に食べてられなかった。
注文した後にポケベルが鳴り、
あの報告が無いと怒られ、
食事しないで会社にすぐに戻った。
毎日、生きた心地せず、
いつ連絡があるかとビクビクしながら
お風呂も長く入れなかった。
社員もよく怒られ、
泣いている姿をよく見かけた。
気に入らないと
2週間でも毎日社長室に呼ばれ、
ガンガン文句を言われる。
余りにもかわいそうなので
かばうと倍返しを食らった。
仕事よりその対処がしんどかった。
そんな形で怒ると遺恨が残ると常々感じていた。
だから、絶対に社員を怒らないと決めた。
二度と同じ失敗をしない為に
どうするかを検討させるようにした。
そして、決め事をしてそれを徹底させた。
自分たちで考え、
自分たちで決めたルールですから
失敗も出来ない。
やらされている感より
やっている感の方がいい。
失敗を責めないで、
失敗させるような仕事をさせた
経営者に問題が有ると
思った方が正解である。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する戦術と戦略を心得た経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
朝から晩まで一生懸命仕事して
頑張っているのに
全く儲からないと嘆く経営者もいる。
よく話をしてみると
確かに朝早くから夜遅くまで
必死に働いている。
時間だけは目一杯働き、
毎日フラフラになっている。
食品販売をしている経営者ですが
従業員と一緒に
売上を上げるために
必死に動き回り営業をしている。
毎日の業務に追われ
今日・明日・明後日ぐらいの事しか
考えれれない状態である。
つまり、目先の事ばかりに追われ
1か月先・半年先・1年先・3年先など
全く考えてない。
経営者であるのに
いち従業員になっている。
売るための戦術ばかり考え、
会社の戦略が全くない。
将来を見据えて
会社としての戦略が無い。
だから、忙しいのに儲からない。
ライバル会社の事も調査もしてない。
お客様の事もよく知ってない。
しかし、自分は一生懸命頑張っていると
勘違いして、愚痴ばかりこぼす。
ライバル会社に勝つために何が必要か
お客様に自社を選んでもらう理由は何か
この2点が分かってないと
勝ち抜けるわけがない。
そこを明確にしないで
とにかく頑張れば何とかなると
勘違いしている経営者も多い。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 成功する素直な経営者
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
穿った目で見て
素直さが無い経営者は
何処かでつまずく。
成功する経営者を見ていると
素直な気持ちで
物事を見て、吸収している。
だから、良い情報が入ってくる。
いい周りが集まってくる。
悪いところを指摘されて
素直に受け止めて
すぐに改善しようとする。
若い将来性豊かな経営者が
一時的な落ち込みで
資金調達が出来なくて
落ち込んでいた。
素直で、やることをすぐするし、
質問もまめにしてくる。
状況がわかり易く
指示もし易い。
愚直な実践をしてくれる。
こちらとしても
何とか頑張って欲しいと
力も入ってくる。
素直な心と愚直な実践が
明るい未来を開く扉の鍵を
与えてくれる。
素直な経営者を見ていると
将来大きく化ける
と予想される企業になる。
経営者は素直でないと
経営者も企業も変貌しない
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
◆ 出版記念セミナー
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥
★★少人数限定セミナー★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■東京会場■■
2017年4月5日(水)18:30~20:30(受付18:00~)リロの会議室飯田橋
2017年5月20日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
2017年6月17日(土)13:00~15:00(受付12:30~)リロの会議室飯田橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■大阪会場■■
2017年4月22日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
2017年7月29日(土)13:00~15:00(受付12:30~)大阪AP大阪駅前会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■福岡会場■■
2017年4月15日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP博多駅前シティーセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■北海道会場■■
2017年5月13日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKP札幌カンファレンスセンター会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■仙台会場■■
2017年6月10日(土)13:00~15:00(受付12:30~)HUMOS5ヒューモス5会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■名古屋会場■■
2017年7月8日(土)13:00~15:00(受付12:30~)TKPガーデンシティー名古屋新幹線口会場
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○参加費:6000円(出版記念割引で12000円を半額に)
*詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://jlifesupport.com/newsite
■■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
■■ 成功のポイント ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆『まだ大丈夫、必死になる必要はない、
という時期から準備しておくことが大切です。』
多くの人を見ていると、お尻に火がつかないと動かない。
それが間違いだ!という事に早く気が付いてほしい。
◆『チャンスは自分から拾いに行くものだ!』
成功する人は、必ず能動的に動き、自分でチャンスを広げている。
目の前のチャンスをつかみ切れないで、逃げていてはダメだ!
やってみないとわからない。
◆『決断力のなさが、後の大きな損失を招く』
決断し、前に進めばいい。失敗すれば修正すればいいだけ。
決断できず、問題を放置する罪の大きさを知らないといけない。
◆◆◆最悪の状態を予測し、最高の準備をしておくこと◆◆◆
*再生には、確かな戦略と準備期間が必要です。
だから、勇気ある一歩を早く踏み出すことが大切なのです。
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★お知らせ★
メルマガ登録者・セミナー申込者・名刺交換させていただいたご縁のある方に
メルマガを発行させていただいております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
※配信解除をご希望される方は、下記をクリックしてください。
http://1lejend.com/d.php?t=###tourokuid###&m=###mail###
お手数ですが、下記へ配信解除の希望と氏名及びアドレスを
メールにてお送りください。
システム上再配信になる場合があるので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。
送り先: info@jlifesupport.com
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Jライフサポート 代表取締役 三條慶八
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〒102‐0071 東京都千代田区富士見2-2-11 INOUEビル5F
TEL 03-6261-3080 FAX 03-6261-3081
e-mail:info@jlifesupport.com
URL:www.jlifesupport.com
Facebook:http://facebook.com/keiya.sanjo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━