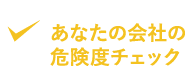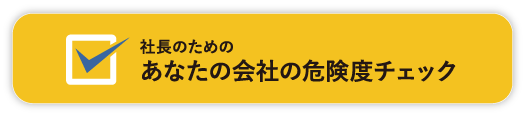其々の経営者には、事業に対する思いがある。長年の歴史があるからです。
反対に金融機関は、会社をそういう目線では見てない。
マニュアル通りしか見ない。
温情を持って見て手を差し延べて失敗した時の責任を負いたくない。
自分の保身しか考えない。
私自身も阪神淡路大震災後、親の為に命がけで自力再生した。
親の事業に対する思いと葛藤し乗り越えてきた。
「親のプライドと生きがいを守る」これに徹してきました。
両親の自宅も最終的に守れた。経営者が相談に見える時に
年老いた親に今まで住み慣れた家を出て行けとは言えないと
苦悩している気持ちがわかる。
守れるものなら守りたい。万が一の時には覚悟が必要です。
前に進むために、捨てる勇気と決断力が経営者や親にあれば、
金融機関との交渉も大きく違ってくる。
そこがネックになると、決断できず、動けず、死を待つしかない。
死すれば、自宅も無くなるのに決断が出来ない。
将来取り返すんだと言う気概を持って臨むぐらいでないと何も残らない。
捨てる勇気とその決断力がその後の人生に大きく左右する。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!
日本の企業の97%が中小企業です。
その中の多くの企業が、粉飾決算をしていると言われている。
一番の問題は、粉飾を続けて真の会社の姿が見えなくなり
判断を間違ってしまう事です。
売上・利益を上げる努力するより、粉飾をして操作した方が楽になる。
また、粉飾すれば何とかなるだろと甘い考えになってしまう。
人間と言うのは、楽な方を選んでしまう。
最後に行き詰まり策も無くなり粉飾が露呈してしまう結果になる。
そのような事が無いように中小企業経営者として先を見据えて考え行動する事です。
粉飾する原因は先が見えず、早めに手を打てず困り果てて粉飾で取り繕い
金融機関の融資を受けようとする。
だからこそ、最悪の事を想定し最善の策を講じる事が大切です。
粉飾しているといつかは銀行にバレて融資もストップになる。
銀行へ月に1回PL・BSを持って説明に行く努力をすることが粉飾をせずに、
信頼を得る正当な方法です。
粉飾による後々の代償が大きい事を自覚し、真摯に事業経営をしていく事の方が
大切です。
年間の資金繰り・利益計画など常に先を予測した経営をし、
最低半年を見据えた資金調達を考えておく必要があります。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!
「銀行とうまく付き合う方法を教えて欲しい」と中小企業経営者によく聞かれる。
「取引銀行に貴方のファンをたくさん作ってください。」とお答えしてます。
私は大学入学と同時に親父の会社に入社し、皿洗いから調理補助、営業、
そして、経理財務など何でもしました。
大学生の分際で資金繰りもして銀行交渉もし、借入もした。
そして、140億まで借りる事になった訳です。
そんな経験から言うと、いかに銀行員と関係性を構築しておくかが大切です。
銀行員のプライドを尊重し、色々な話を聞く。
相手の助けになることを協力する。
その上で、自分自身の経営理念や商売に対する思いを伝え、経営者として
認められる存在になり、ファンになってもらうことがすごく大切です。
そういう人たちを銀行内に増やせば、様々な場面で協力してくれます。
一番有り難かったのは、自力再生している時に、私が知りえない情報を
提供してくれました。
金融危機で破たんし、追いやられた銀行員が昔お世話になったと
自分ごとの様に動いてくれました。
自分1人ではやれることは限られています。いかに多くの協力者を
得て実行に移せるか?これが大切だと思います。
地道な努力には必ず花が咲きます。ファンを作って下さい。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!
事業計画書を作成している会社も多い。
しかし、何の為にするのか?ただ、金融機関に出す為に
儀礼的なものとして作成している会社も多い。
せっかく作るなら、身になる方法を考えた方が有効。
作成する意義は、何なのでしょうか?
会社の3~5年後の具体像を描き方針を決め、実現させるための
具体策を明確化させるもの
つまり利益と売り上げを社長が決定し、それに対して各部門がどういう策を
考えて実現させるかその計画書づくりだと考えている。
経営者が脳から汗が出るほど悩み苦しみ考える事が大切。
人間は、目標を定めないと直ぐに手を抜いてしまう。
経営者自身を律する為に、会社を律する為に社員を律する為に必要な事だ。
事業計画を作る事が目的ではない。どう活かすかが、とても重要である。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!
会社の歴史や事業規模からして保証協会融資しかないのは
おかしいと思われる会社の経営者が相談が来られた。
過去から検証しているとその事実がわかりました。
東北の大震災、リーマンショック後保証協会融資の枠が大幅に拡大された。
多くの企業が借入申請すると何千万というお金が融資された。
それに目を付けて資金がすぐに必要で無い企業にも銀行は借入申請をさせていた。
借入をさせるのは問題ないが、以前に貸し付けていたプロパー融資の回収に利用した。
中小企業なら融資を受けた資金は有効に活用すべき大切なお金である。
無理やり返済資金として回収された。
多くの中小企業は、今後の事を考え泣き寝入りして従っていた。
融資したお金を直接回収すると違反行為にあたる。
わざわざ他行の口座にお金を移動し、再度その銀行口座に資金を戻し
回収するという姑息な事をしていた。
多くの金融機関が自分たちのリスクを減らす為に保証協会融資を利用し、
回収に勤しんでいた。
本来融資を受けて,資金的に余裕が出る筈だった。
融資を受けた資金を回収されたお蔭で現在、資金繰りが苦しい。
必要な時にはお貸ししますからと融資を受けた資金を回収した。
全くの詭弁であった訳です。
本来なら中小企業の支援のための融資が金融機関のリスクを減らすための
融資制度に代わっていたのです。
中小企業救済ではなく、銀行救済融資になっていた。
多くの企業の相談を受けているとこのような実態が結構多い。
しかも、積極的に推し進めていた地方の金融機関もある。
保証協会付け融資は銀行のための貸付制度である。
何とか制度改革しないといけない。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!
商売をしていると目線がおかしくなることが有る。
会社都合・経営者都合・社員都合で物事を判断して進めようとする。
相手の立場に立ってどう思っているのか
どう感じているのかどうしてほしいのか何を望んでいるかを
察しなくてはいけない。
求めているお客様の気持ちがわかれば失敗することなどないはず。
企業側や経営者側の都合で物事を決めている事がある。
だから、お客様の心は離れる。
純粋なお客様の希望を当社の決まりでと言われると無性に腹が立つものです。
相談に来られる経営者にも自社の製品にほれ込んで
周りが見えなくなっている方もいる。
経営者の考えているビジネスモデルは成功するのは当たり前と
考えている方もいる。
商売の基本は、対象となるお客様が何を欲しているのかを察知する事だ。
それがブレだすと会社の状態がおかしくなる。
経営者が考えた商品やサービスがなぜ売れないのかと
相談に来られることがある。
説明しても分かってもらえない事がある。
最後には、お客さんが理解できないのだとお客様に非があるようないい方をする
間違った考え方の経営者もいる。
謙虚な気持ちでお客さんに接しないと見えるべきものが見えなくなる。
お客様目線がどこまで極められるかで会社の将来は決まる。
●無料個別相談のお申込みは↓↓
【個別相談 | 経営コンサルタント三條慶八】
株式会社 Jライフサポート 三條慶八
=======================
◆中小企業経営者のためのYouTubeチャンネル開設◆
https://www.youtube.com/channel/UCfTHfz-y4hLXpOlXYux98fg
▲【徹底解説】借金を処理して会社を再生させる方法 大公開!